

主催:益子町文化のまちづくり実行委員会、益子陶芸美術館
協賛 : 特定非営利活動法人ましこイーまちネット
後援 : ブリティッシュ・カウンシル、下野新聞社、とちぎテレビ、栃木放送、エフエム栃木、真岡新聞社
| 開催期間 | 2020年6月28日(日)-11月8日(日) |
|---|---|
| 休館日 | 月曜日(祝休日の場合は翌日) ※秋の益子陶器市中止により、11月2日(月)休館、5日(木)開館。 |
| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時 [11月は16 :00まで](入館は閉館30分前まで) |
| 入館料 | 大人600円(550円)、小中学生300円(250円) *( )内は20名以上の団体 / 65歳以上は300円(要証明) |
「英国で始まり」とは、濱田庄司 (1894~1978) が自身の半生を回顧した有名な言葉「私の陶器の仕事は、京都で道を見つけ、英国で始まり、沖縄で学び、益子で育った」の一節です。
濱田は今から100年前の1920年、バーナード・リーチ (1887~1979) とともにイギリスに渡り、南西端の港町セントアイヴスに東洋風の登り窯を築きました。そこから、イギリス近代陶芸の礎となったリーチ派の作家たちが生まれます。濱田の「英国で始まり」という言葉は、濱田自身の陶芸家としてのキャリアの第一歩ばかりでなく、イギリスにおけるリーチ派の始まりにも繋がっているのです。
本展では、リーチ派をはじめとする近現代イギリスの個人陶芸 (スタジオ・ポタリー) の系譜に焦点を当てます。イギリスでは、長い歴史の中で工芸的な用のものを制作するのは“職人”であると意識づけられてきました。濱田とリーチがセントアイヴスで陶芸を始めたことで、いかに“陶芸家”という意識が育ち展開してきたのか、作品を通して見つめます。
一方で、日本において陶芸は、桃山陶の時代からただの“モノ”ではない、ある種の美意識をもって実用品以上の評価をされてきました。そのような日本人としてのバックボーンを持ちながらもイギリスで始まった濱田の陶芸が、日本でいかなる影響を与えたのか、本展では、濱田以降の益子の近代陶芸の一端を紹介します。
イギリスと益子、二つの地で切り拓かれた陶芸の醍醐味を同時にみせる初めての展覧会です。現代イギリスを代表する作家から、益子の礎を築いた作家まで、60名による作品約170点が一堂に会します。
 |
 |
| 濱田庄司 《壺》 1923年 アベリストゥイス大学美術館 Ceramics Collection, |
バーナード・リーチ 《楽焼飾皿》 1919年 益子陶芸美術館 © The Bernard Leach Family, DACS & JASPAR 2020 E3749 |
 |
 |
| 松林靏之助 《練込小鉢》 1924年頃 益子陶芸美術館 |
マイケル・カーデュー 《鷺文楕円皿》 1928年 アベリストゥイス大学美術館 © The Estate of Michael Cardew Ceramics Collection, |
 |
 |
| 加守田章二 《曲線彫文鉢》 1970年 栁澤コレクション |
木村一郎 《象嵌陶筥》 1940年 益子陶芸美術館 |
 |
 |
| ハンス・コパー 《ポット(ティッスル・フォーム)》 1975年 兵庫陶芸美術館 |
エドモンド・ドゥ・ヴァール 《things exactly as they are》 2016年 益子陶芸美術館 |
横堀 聡
1853(嘉永6)年に始まるといわれる益子焼は、信楽の流れ職人から技術を学んだ笠間の焼物から分派し、信楽焼の技法を益子の土に置き換えたような平凡な田舎の焼物だった。歴史の浅い益子焼が北関東の田舎町でありながら長い歴史ある他の窯業地に遅れることなく、昭和の初めには個人陶芸家が活躍を始める大きな理由の一つは、1924(大正13)年に英国から戻った濱田庄司に起因する。
濱田は帰国すると、イギリス滞在中工芸村ディッチリングを訪れた時に想起した益子へ向かった。イギリス滞在中の濱田作品には「庄」の落款が入れられたが、益子へ入ってから濱田は作品に落款を付けることを止めた。その理由を柳宗悦がこのように述べている。「まして焼物の如き、人間を超える力が多く働く仕事を、どうして自分一人の力に依ると呼び得るであろう。近代では誰も彼も落款をするが、この習慣は昔にはなかった。 -中略- どうして一度無銘の心境に成り下って、仕事をそこから生みえないのか」(註1)。濱田は一般的な粘土の上質を求めた訳ではなく、益子の土を使いこなすことで生まれる益子ならではの陶芸を展開したのである。だから濱田は益子の土を三流とは言っていない。
当初、自宅を持たなかったこともあり、濱田は5 年間頻繁に益子から沖縄へ通った。沖縄に滞在することで、沖縄の無垢な文化や陶芸から多くを学んだ。沖縄は東南アジア文化の交差点であり、その中から生まれた独特の沖縄の文化が濱田の心を捉えた。沖縄とイギリスでの経験で、濱田の陶芸は中国風や朝鮮陶器風から方向を変えて、自分の進むべき方向を定めていった。ただし、濱田の陶芸は大きく方向転換してゆくが、それまで蓄積した陶芸の全てを無くした訳ではなく、イギリス的なものが加わることによって新たなものが生まれたと考えるべきであろう。例えば、イギリスで試したスリップウェアの線模様は、1950年代半ばにそれまで蓄積した知識や体験によって流掛けの技法として現れる。
1930(昭和5)年、家と登り窯を構え、本格的に作陶を始めた。当時、濱田が関わっていた民藝運動の影響もあり濱田の陶器が売れると、多くの窯元は似たものを作り始めた。結果、益子焼は濱田焼になったと思えるくらいの変化があったように思える。濱田焼という言葉は一般的ではないが、1900年代半ばの益子は濱田の亜流と思える焼き物で溢れていた。また陶芸家を志し、戦後濱田の門を叩いた若者は多い。最初期に濱田に師事した村田元、島岡達三、瀧田項一、阿部祐工、濱田晋作らは濱田に技術だけでなく、濱田の精神も共有したのである。であればこの時期、濱田に学んだ彼らを濱田派と呼ぶことも可能だろう。例えば、村田のように益子の土に深く依存する陶芸は、まさしく濱田が「もし適切な陶土を産する土地を見つけられたなら、陶工はそこに自分の仕事場と窯を持たなければなりません」(註2)と提言していたように、益子の土に深く傾倒したような作風だった。島岡は益子で縄文象嵌という装飾技法を一生かけて熟成し完成したことで、濱田に次いで重要無形文化財技術保持者に認定された。瀧田は触れれば手が切れそうな白磁ではなく、温かみのある白磁を理想とした。理知的な瀧田を柳宗悦と濱田がパキスタン芸術大学の講師に推挙し、3年間南アジアに赴任することになる。そこでの民族文化との出合いが瀧田の作調の一つとなったのである。阿部は益子での修業を終えた後、九州で民藝運動を通して自身の陶芸を成熟させていった。濱田の次男晋作は父庄司の跡を継ぎ、濱田窯の釉薬、土を守りながら、躍動的な庄司とは異なる静的な陶器を作っている。
益子における個人陶芸の芽生えは単に濱田が益子を作陶の場としたからという単純な文脈では語れない。地元の素封家に生まれた木村一郎は旧制中学に入る頃には窯元の知人たちと焼物作りを試みていたという。裕福な家庭に生まれた木村が、自宅内に飾られている日本画や工芸品に興味が湧いたのは容易に想像がつく。河井寬次郎の陶芸などを鑑賞するうちに、居ても立ってもいられず周囲の反対を押し切り、1937(昭和12)年京都の商工省設置の国立陶磁器試験場(註3)の第20期伝習生として京都で作陶を学んだ。この京都陶磁器試験場に始まる試験場は、当時京都が美術工芸の近代化の中心地であった(註4)ことを示している。この試験場について五代清水六兵衛は「ながい慣習的な制作のみにふけっていた京焼の業界に、この試験場が開設され、その溌溂とした活躍は、たしかに業界にめざましい反響を呼び起こし」(註5)と紹介している。また、八木一艸は京都市陶磁器試験場の同窓生である楠部彌弌らと共に1920(大正9)年革新的陶芸結社「赤土」を結成したメンバーの一人である。北関東の田舎の窯業地益子とは違い、長い伝統をもつ京都の工芸界に於いては前述の五代清水六兵衛の言葉のように古い慣習的な制作を打ち破り革新ともいえる新たな陶芸を目指す動きが既に始まっていた。この時期京都では国画創作協会の結成により旧態依然とした画壇にたいして新しい日本画を求める運動が絵画界にも起こっている(註6)。この新たな陶芸を目指す意思は、一艸の息子 八木一夫もやがて1948(昭和23)年「走泥社」を結成して父一艸の意思を引き継ぐかのように前衛的な思考が表面化する。京都ではこの動きが更に「四耕会」の結成へと続くのである。この様な京都で木村は八木一艸に興味をもち、なおかつ伝習場では八木一夫と同期生であった。1937(昭和12)年の5月には河井寬次郎がパリ万国博覧会においてグランプリを受賞する。木村は五条坂の登り窯の窯詰めを手伝ったりした時に、河井の姿を身近に見つめる機会もあったろう。これらのことは当時京都にいた木村にとって少なからず刺激になったはずである。このような先進性を京都で体験した木村は益子に戻り異端児のように、これまでの益子焼にはない陶芸を展開し始めるのである。
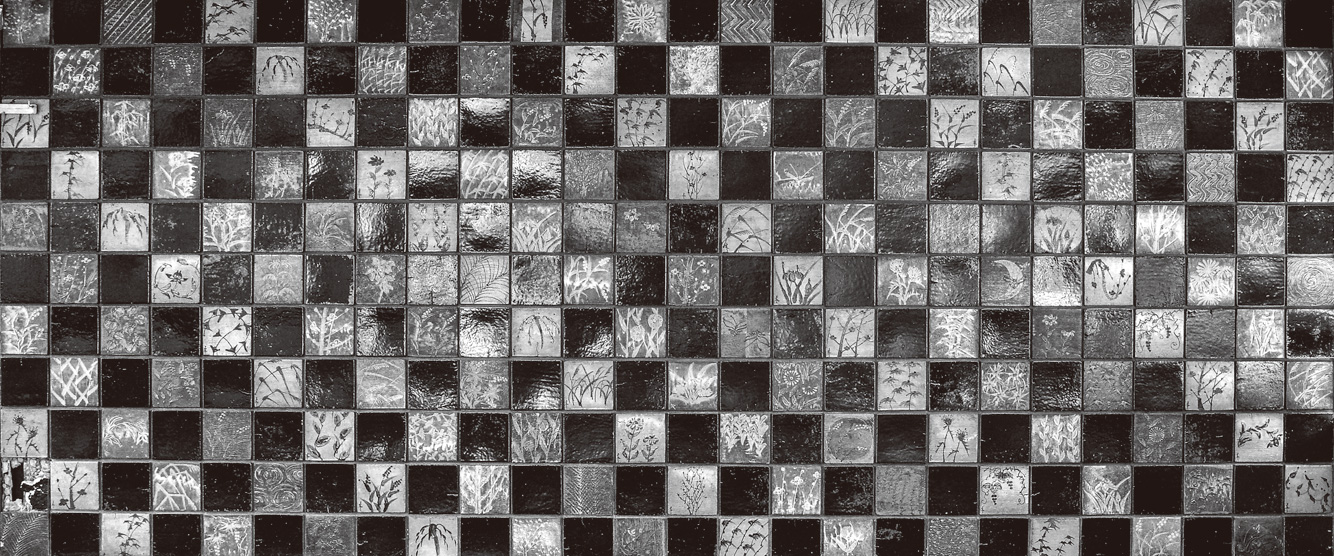
木村一郎《陶壁》1965年頃
戦後、兵役を終え益子に戻った木村は1946(昭和21)年に登り窯を築窯。窯出しには濱田がその都度立ち寄ったという。もしかすると、木村の陶芸に他の益子の焼物屋とは違う作家性を感じ取っていたのではないだろうか。ただし、何故か木村の辰砂と練上げには否定的であったらしい。その理由は今となっては定かではないが、河井寬次郎が多用した辰砂と練上の技法を濱田が益子で使うことはなかった。木村の陶器はガレナ釉に繊細な筒描きの文様、練上げ、辰砂釉、ガラス釉等々様々な試みがあり、作ってみたい焼物が沢山あって試しきれなかったという。昭和40(1965)年頃にはまだ一般的でなかった陶壁(写真)を制作するなど益子の先駆的な活動をしていた。この多様な試みが無知な周辺からかまびすしく批判されることもあったようだ。木村の初期作品を見ると、筒描きによる繊細な線や点による装飾は1937年の京都時代の《飴釉スリップ菓子組皿》(No.144)に既にみられ、高い完成度を示している。益子に戻った翌年には益子では作例がない練上げの技法による《飴釉練上手角組皿》(No.145)も作っている。同じく辰砂釉も木村が益子で最初に始めた一人である。益子の木村は濱田と別の文脈を持った個人陶芸家であることをあらためて確認したい。当時の木村の活躍を主だった展覧会で観てみよう。1955(昭和30)年の「第4回現代陶芸展」において木村は《黒釉抜絵角鉢》《草繪大皿》を出品しているが、この展覧会には益子と関係深い河井寬次郎をはじめ、京都の宇野三吾、清水六兵衛、楠部彌弌、林康夫、近藤悠三、瀬戸の加藤嶺男(岡部嶺男)、河本五郎、萩の坂倉新兵衛、他に加藤藤九郎、加藤土師萌、藤本能道らが名前を連ねる(註7)。1959(昭和34)年の第6 回伝統工芸展には加藤嶺男や山本陶秀、中里太郎右衛門、辻新兵衛、坂倉新兵衛、辻晋六、原 清らとともに奨励賞に輝いている。金重陶陽、濱田庄司、宇野三吾、清水卯一、大樋長左衛門らも同様の立場で展示されていた。ちなみに木村の作品は《鉄釉面取壺》であった(註8)。同じ年5月23日から東京国立近代美術館で開催された「現代日本の陶芸」展(註9 )にも出品依頼を受け、《練上手壺》を出品している。この展覧会は日展派、新匠会、民芸派、前衛派、日本工芸会、其の他と区分けされ当時の日本陶芸を俯瞰するような大展覧会であった。そこにも漏れることなく木村は選ばれていたのである。1964(昭和39)年8月22日から東京国立近代美術館で開催し、九州石橋美術館、京都近代美術館、名古屋愛知県立美術館へと巡回した「現代国際陶芸展」にも出品を依頼されている。このように昭和30年代の木村の活躍は目を見張るものがある。では何故昭和40年代を境に木村の名前を展覧会で見ることがなくなったのか。1965(昭和40)年、まだ陶壁という言葉も珍しかった時代に陶壁を制作し、宮内庁東宮御所から《雪白釉角大鉢》、《竹文降雪絵角皿》の注文を受ける(註10)栄誉を得ながらもこの年、木村は工芸会から脱会する。その理由は工芸会のある人物から《練上壺》を「それは石の仕事じゃないか」と言われたことが原因であったと云う。皮肉なことに、後に練上げ手でいわゆる人間国宝になった茨城県の陶芸家松井康成は最初に木村から練上げの手解きを受けたのだった。工芸会を脱退したことで、いつの間にか木村の名前は日本の近代陶芸史の表舞台から消えていったのである。
もう一人忘れてはならないのが松原直之という木村の弟子である。松原は木村から名刺を預かり1958(昭和33)年、京都の八木一夫を訪ねた。八木の下で1年程働くうちに痩せていった松原の健康を気遣い、内弟子として八木の家で働くように誘われたという。このさりげない行為に八木の人柄を感じずにはいられない。それから2年間、八木の作陶の手伝いに励んだという。特に黒陶焼成のために八木一夫の父一艸のところへ焼成前の作品を運ぶ度に、京都風の食事を分けていただくことが何よりの楽しみだったという。この時の経験と共に陶芸家という存在を知って個性の表現をしなければならないという気概を植え付けられたのである。3年の修業を終えて益子に戻った松原は、濱田の真似ではない独自の並白釉を自身の陶表現として完成するのである。
昭和30年代になると益子町深田にある塚本製陶所に研究生制度が作られ、将来を嘱望される若者が次々と益子に入り作陶を始める。昼間は塚本製陶所の数物などを作り、それ以外の自由な時間には自分の好きな陶器を作ることが許されていたし、古株の職人からロクロや釉薬の調合方法、焼成技術などの実践を学ぶことが出来たうえに、住居まで提供されたという。益子の人材育成には昭和30年代のこのシステムがなかったら濱田の次世代は育たなかったと思われる。この頃の益子はまだ貧しく半農半陶の生活が大半を占める時代であったが、塚本製陶所が始めたこの制度によって、町外から陶芸家志望の若者が益子へ移り住むことが出来たのだ。その意味で塚本製陶所の研究生制度は当時の益子にとって画期的であった。伝統ある窯業地に比べると歴史の浅い益子が次の世代へと人材を育てるために弟子を抱える余裕があったのは濱田庄司、島岡達三他わずかな陶芸家しかなかったのである。
濱田の次世代の特徴はその多くが美術大学あるいは大学卒の人材が多かったことである。(勿論、濱田庄司の卒業した東京高等工業学校は後の東京工業大学であるが)京都市立美術大学を卒業した加守田章二、その美大の後輩・瀬戸浩、東京で大学在学中に濱田の作品に感動し陶芸家を目指した廣崎裕哉、東京藝術大学陶芸科1期生の吉川水城などが濱田に続く次の世代として益子に入ってきた。益子の栃木県立窯業指導所の技師をきっかけとして益子で作陶を始めた吉川以外は、塚本製陶所の研究生として益子に入って来た。
加守田章二が京都市立美術大学を卒業してきたことを考えると、木村が益子へ持ち込んだ京都の陶芸文脈に含むことが出来ないだろうか。加守田が茨城県の大甕陶苑に就職して益子へ来るきっかけとなったのは木村一郎と日立製作所窯業碍子課長の辛島詢逸が知り合いだったことである。当時、日立製作所では益子の木村一郎の陶器を贈答品として木村から購入していたのである。発案は誰かわからないが、贈答品の陶器を日立製作所が自前で作るために日立製作所は大甕陶苑を立ち上げる。その時に美術陶焼成の技術員採用の要望が京都市立美術大学にあり、先輩の竹内彰と共に加守田が技術員として茨城県の大甕陶苑に就職した。加守田は大甕陶苑の技術部員を休職という異例の計らいで、塚本製陶所の研究員として益子に滞在することになったのだ。辛島が加守田と木村との縁を取り持ったのである。しかも加守田は益子へ来た当初、木村家の離れに間借りすることにしたのである。やがて家内制手工業のような小規模の生産形態が多い益子の窯元は加守田にとって個人作家のそれと似た制作形態に見えたかもしれない。結果、益子への移住を希望して大甕陶苑を正式に退社し、益子での作陶生活が始まった。その後の加守田の活躍は前例のない陶芸の境地を切り開き、1970(昭和45)年岩手県遠野の土を使い焼成した《曲線彫文》作品は至高の陶表現として今や伝説にならんとしている。加守田陶芸の基本となる焼締めは単なる無釉の焼締めではなく、表面を耐火度の高い土で覆い、焼成後その土を剥がすという方法によって生まれた焼締め。その陶肌に施される文様は1970年頃から毎年のように大きく作調を変えた。加守田のファンはその変化に期待し、加守田の個展が開催されるギャラリーに前日から並ぶ者まで現れたという。
京都市立美術大学の加守田の後輩・瀬戸浩は加守田の勧めで益子に入り陶芸をすることになったが、目の前にいる孤高の存在加守田にどうしても影響されずには作陶が出来なかった。瀬戸は1970(昭和45)年招待されてアメリカへ渡る機会を得た。アメリカの体験を通してラジカルな空気を益子へ持ち込んだ一人である。瀬戸の陶芸は線條の彫文から凹凸の無い銀や金のストライプに特化して器形と文様の関係を突き詰めていった。そして益子に於いて最初に《ストライプの輪》(No.168)のような、器ではなく純粋な造形物としての陶芸を作ったことの意義は大きい。
廣崎裕哉は土という素材から離れ益子で磁器を始めた嚆矢である。単なる磁器ではなく作品の中には牙白瓷(No.169-171)と命名した象牙色の磁器に廣崎独特の造形世界を表現したものがある。濱田や加守田という全国的に認められた陶芸家を身近に、独自の個性を作ることの困難な中で、土物でなく磁器によって、しかも牙白瓷によって廣崎の世界を築いたことは特筆できる。
吉川水城は東京藝術大学卒のエリートとして窯業指導所の技師から独立して豊富な化学知識をもとに益子の黒釉を改良し、晩年には生涯をかけて追い求めた、蕩けるような黒釉の焼成に成功した。この黒釉の中に溶け込むような花文様は、幽玄という言葉がこの吉川の陶芸の為にあったかのようである。この濱田の次世代はある意味益子の第2の黄金期である。生活よりも陶芸が一義的な意欲的な人材が集まっていた。本展で紹介しきれなかった安田猛や小滝悦郎、肥沼美智雄、坂田甚内などがいた。
近代陶芸史の中で個人陶芸という存在が出現したが、西洋的な文脈によって生まれた個人陶芸の登場とは別に、日本にはもう一つの個人陶芸があるのではないか。例えば樂家のように桃山時代から16 代以上続く焼物をどのように説明すればよいのだろうか。樂家それぞれの代に個の表現が無かったのであろうか。元来個々の人間には個性がある、逆に言えば個性があるから人間である。その人間が作る焼物には必然的に個性が反映されて然るべきである。近代陶芸史における陶芸家の成立以前に個性的な焼物を作る存在があったことも事実なのである。そこには日本独自の作家性の成立があるような気がしてならない。日本の近代以前に" 陶芸家" に代わる言葉や存在があったはずである。樂焼は16 世紀後半初代長次郎によって始められた。装飾を廃した茶碗は当時「今焼」と呼ばれたことから推察すると前衛性が感じられたことは想像に難くない。単なる伝統様式の継承ではなく、それぞれの時代感覚を反映しながら、それぞれの代は新たな今を生み出し、樂家の焼き物を続けてきたように、個の創作は古くから日本に存在したと思う。何故ならば伝統は個の革新の積み重ねであるからだ。
(益子陶芸美術館学芸員)
| 註1 | 濱田庄司『窯にまかせて』株式会社日本図書センター、1977年。 |
| 註2 | Bernard Leach, HAMADA POTTER, KODANSHA INTERNATIONAL,1975. |
| 註3 | 前身は濱田や河井が籍をおいていた京都市陶磁器試験場。1919(大正8)年に国立に昇格。 |
| 註4 | 前﨑信也『大正時代の工芸教育』5頁、宮帯出版社、2014年。 |
| 註5 | 前掲書、6頁。 |
| 註6 | 松原龍一「八木一夫の軌跡」、『没後二十五年 八木一夫展』所収、日本経済新聞社、2004年。 |
| 註7 | 『第4 回現代陶芸展』図録、日本工芸会、1955年。 |
| 註8 | 『第6 回日本伝統工芸展』図録、日本工芸会、1959年。 |
| 註9 | 『現代日本の陶芸』、国立近代美術館、1959年。 |
| 註10 | 「皇太子さまのご注文品」、『下野新聞』、1965年4月23日付。 |
※文中の「No.」は、本展図録の作品番号
松﨑 裕子
スタジオ・ポタリーとは、工場や製陶所で大量生産される陶磁器に対し、個人ないし少人数で構成される工房で制作する、創作的な表現としての陶芸を意味する。狭義には、20世紀初頭の欧米において、美術学校で芸術教育を受けた世代により展開された工芸運動を指す。英国スタジオ・ポタリーの始祖の一人とされるバーナード・リーチは、自らの根幹となる思想として「東と西の結婚」というヴィジョンを掲げた。その始まりは、イギリス帰国前の1910 年代に遡る。リーチは日本で楽焼と出合い、自国のスリップウェアの古作に魅了され、宋と高麗の陶磁器を研究し始め、美の規範とした(註1)。
リーチは六世尾形乾山に師事した2年後の1913年に、富本憲吉を通じてロマックス著『風変わりな英国古陶(Quaint Old English Pottery)』を手にし、スリップウェアの世界に熱中する。渡英直前、東京麻布の黒田清輝邸の東門窯で焼成したのが《楽焼飾皿》(No. 3)である。縁の文字や模様にイギリスのトフトウェアからの感化を窺わせる。
リーチの初期作品は鑑賞される芸術作品としての性格が色濃い(註2)。1920年代半ばから後半頃まで、リーチはセントアイヴスのリーチ工房を拠点に、デルフトの錫釉風の色彩豊かな楽焼や、ガレナ釉の筒描きによる飾皿の優品を発表した(今日、特に日本でリーチ=スリップウェアのイメージが強いのはこれらの作品によるのだろう)。一方で、リーチの関心は装飾性の強い軟質陶器から、実用性があってかつ高貴である(と当時思われていた)高温焼成のストーンウェア(炻器)に向かい、リーチ工房はストーンウェアの制作に重心を置く。リーチの画才が発揮されたストーンウェアの装飾タイルは当時から好評であった。《鉄絵組合せ陶板》(No.8)はリーチが得意としたモチーフ(柳、動植物、壺、登り窯、井戸など)の模様で構成され、リーチの装飾のエッセンスが凝縮されている(註3)。たしかに、リーチは画家でもあり、陶芸作品においても見事な絵画的表現を展開する。しかし、リーチがやきものというメディアで見出したのは、素材とフォルムと調和した模様のあり方であり、絵画的思考に基づく描写とは別物であることにもあらためて注目したい。
西洋において、19世紀後半から1920年代にかけては芸術概念が揺らいだ時代である。イギリスでも芸術の自律性を主張する立場と、芸術と社会の接点を主張する立場が現れ、後者のジョン・ラスキン、ウィリアム・モリスらに端を発するアーツ・アンド・クラフツ運動の一環で、イギリスには工芸村が生まれる。リーチを含むスタジオ・ポター(個人作家)が誕生する背景には、こうした運動にも連なる、美術と工芸のジャンル間のヒエラルキーの問題がある。陶芸や工芸の地位向上、工芸の「アート」への位置づけ、機械的労働や近代産業のあり方への懐疑、延いては物質文化や「もの」の在り方への意識の高まりが、同時多発的に生じた時代である。
スタジオ・ポタリーの起点には諸説あるが、黎明期は19世紀の終わり頃とされる。現在はリーチら1920年代以降のスタジオ・ポタリーと区別して彼らの仕事を「アート・ポタリー」と呼ぶことが多い(註4)。成形や焼成における一定の創作的表現への志向が認められる点でスタジオ・ポタリーに連なるが、製陶は分業による手工業的な制作スタイルによるもので、そこでの「デザイン」は大量生産が可能であるという考え方などからスタジオ・ポタリーと区別される。過渡期の作家として象徴的なのがマーティン兄弟(1873-1915活動)である。《壺》(No.34)や《鳥像》(No.35)にみられる細密で少々グロテスクな意匠には、ジャポニスムやヴィクトリア朝時代の美意識がみてとれる。
一方で、1880年頃になると、陶芸に対する美的判断の基準において、絵画的な装飾に代わって徐々に土味や技法が浮上する。歴史的背景として、日本の茶道の価値観が輸入されたことが大きい(註5)。明治維新に伴い、旧家から茶道具を含む多くの美術品が流出し、備前、信楽、織部など日本の茶陶が西洋の蒐集家の手元に渡った。釉や造形の侘びた美しさが称揚され、マーティン兄弟の後期作品にも間接的な影響を及ぼしている。20世紀初頭には岡倉天心の『茶の本』が登場し、『ストゥディオ』などの影響力のある専門誌で紹介された。他方、19世紀後半には中国の鉄道敷設工事を機に宋代の良質な陶磁器が大量に発見され始め、ヨーロッパ世界を魅了した。イギリスでは早くも1910年にロンドンのバーリントン・ファイン・アーツ・クラブで古代中国陶磁器展が開かれており、大英博物館陶磁器部門のR.L.ホブソンや有力な蒐集家たちが熱中した。欧州で中国陶磁が人口に膾炙するのはもっと後のことだが、敏感な作り手の間では早々にフォルムや釉薬に関して新たな解釈を生むほどの大きな影響が及んだ(註6)。
初期のスタジオ・ポタリーは、いわば日本の茶陶が準備した美意識を下地としながら、造形的な特徴として中国陶磁の影響が顕著である。うつわの表現は端的に、前時代の華美で写実的な装飾から、釉調や搔落しでみせる抽象表現が高く評価されていく。この時期の重要な作家の一人がウィリアム・ステート・マレーである。リーチがうつわの実用性や作陶における倫理性を視野に入れていたのに対し、マレーはうつわを彫刻と捉え、しばしば作品にタイトルを付け、絵画と一緒に画廊に展示した。すなわち彼は陶芸をもって「アートワールド」への参加を意識していた。レジナルド・F・ウェルズは、元々は17 世紀の英国古陶に触発されたスリップウェアを制作していたが、先の1910年の展覧会を機に中国陶磁風の作風に切り替える。自身の陶器を「SOON」と名づけ、初期スタジオ・ポターたちが好んだ鈞窯の澱青釉を思わせる《壺》(No.37)などを残した。ウェルズには素材のコントロールに苦心した先駆者ならではの実験的な作例が多い(註7)。
マレーは1925年にロイヤル・カレッジ・オブ・アート(王立芸術院、RCA)の陶芸科教官に就任し、後に陶芸科長となる(後進の育成における影響力は大きく、RCAでは後にセラミック・アーティスト、セラミストの意識を持った作家たちが育っていく)。リーチのライバルとされた一方で、濱田庄司とは友好関係を築き、濱田はマレーに刷毛目や糸底の作り方を教えている。
濱田庄司こそ、初期の英国スタジオ・ポタリーのキーパーソンである。濱田のパターソンズギャラリーでの個展を観た大英博物館キュレーターのウィリアム・ウィンワースは、松林靏之助宛ての書簡の中で、刷毛目の技法による濱田の作品に感銘を受け、より日本的な技法を使うことを期待しながら、濱田庄司の作家としての個性、「" 濱田" スタイル」の萌芽を認めている(参考資料No.6)(註8)。東洋陶磁の流行も手伝い、作風や技法、そこに象徴的に映し出される作家性などにおいて、濱田庄司は西洋の陶芸の近代に絶大なインパクトを与えた(註9)。濱田の英国時代作品は、英国古陶や磁州窯、絵高麗風の意匠や造形を特徴とするが、より重要なのは、そうした「装置」としての作風を構成する鉄釉の焼成(No.22)や蝋抜き(No.25)、刷毛目(No.31)などの技法を、当時の現代の生きた表現として見せたことだった。濱田庄司は、独創的な造形作家として欧米の陶芸界に強烈な爪痕を残した。
アーティスト・クラフツマンとしての理想を追ったリーチと、アーティストとして陶芸に臨み続けたマレーの間ではスタンスや思想に乖離がある。(後述する通り、この二つの系譜が共存していくところに英国スタジオ・ポタリーの魅力がある。)しかし造形的に見れば、異質な他者に美の基準を見出している点で両者は同時代的である。それらは、濱田や東洋陶磁が触媒となって生まれた抽象であった。
リーチの後半期の作品は黒釉や白釉など単色を基調とし、形態において優れた作品が少なくない。小鹿田で制作したとされる《櫛目壺》(No.49)の伸びやかな佇まいと飾り気のない櫛目は、『陶工の書』にも掲載されている中世英国の水差を思わせる。磁土による鎬壺(No.55)はリーチの晩年作であり、無骨さと華奢な雰囲気が入り混じる。最晩年のリーチの到達点は、彼自身の言葉を想起する。「世界で最も美しい陶器は、技術上の不完全さに満ちている」(註10)。
今日、リーチ工房は英国現代陶芸の礎と言われる。本展でも、ウィリアム・マーシャルら初期リーチ工房を支えた作家たちを紹介しているが、傑出して重要なのはマイケル・カーデューとキャサリン・プレイデル・ブーヴェリーである。
リーチの一番弟子とされるマイケル・カーデューだが、リーチ工房が東洋陶磁を背景としたストーンウェアに重点を置いたのに対し、少年期からフィッシュリーの作陶に親しんでいたカーデューは英国の古陶、スリップウェアを理念の軸足とした。自国の古作からインスピレーションを得た、現代を生きる陶工としての作陶姿勢は、陶芸の英国性とは何か、英国陶芸の伝統とは何かを問い(註11)、リーチとは異なる意味で多くの追従者を生み出した。
キャサリン・プレイデル・ブーヴェリーは、松林靏之助に学んだ陶芸技術をベースに、自らも灰釉の実験を重ねた。重要なのは、彼女の制作動機が前の世代にみられる中国陶磁や古作への憧憬ではなく、むしろ模倣を忌避し、釉薬の微妙な調子や色彩を、等身大の自己表現の手段と捉えた点にある。生活手段や営利目的ではなく、ライフワークとしてやきものを追求したブーヴェリーには、ある種のアマチュアリズムが根底にある。自己韜晦のない作品世界の純粋な追求に、揺らぎのない芸術性が宿っている。
陶は、土という素材を焼成することで出来上がるが、土という重力のある素材をいかに立ち上げるかという問題を本質的に孕んでいる。立ち上がる姿こそが陶の本質であり、立ち上げ方に作家の個性が宿っている。20世紀半ばになると、イギリスにおける陶表現は、大陸出身の三人の作家を通じて新たな支脈を得た。
ルーシー・リーのうつわの大きな特徴は、ロクロでひいたパーツを組み合わせるという点にあった(註12)。制作工程におけるパーツの分節化は、量産を目的とした合理性の追求という側面もあるが、結果として、形態に対する厳しさの追求に繋がった。すなわちロクロのラインの柔和さが緩和され、かたちにシャープさが加わった。ハンス・コパーもまた、ロクロ成形により、幾何学的パーツを組み合わせたうつわのフォルムをアイデンティティとした。二人とも考古遺物に触発され、プリミティヴな美を起点とした普遍的に受け入れられる造形を獲得していくが、リーがいわば色彩も造形の要素としてみせたのに対し、コパーはモノトーンで質感の追求を際立たせた。
リーとコパーのもたらしたモダニズムは、うつわの表現を構成する「接合(combination)」の手法において表れている。コンビネーションの思想は、造形として表現的なうつわの誕生を予感させると同時に、うつわとうつわを「並置して組み合わせる」という表現の方向、うつわ作品のインスタレーション化へも展開する可能性を孕んでいた。
ルース・ダックワースは、彫刻家として活動を始め、ヘンリー・ムーアとブランクーシに多大な影響を受けた。紆余曲折を経てロンドンの中央美術工芸学校でドーラ・ビリントンらに陶芸を学ぶが、当時の同校ではリーチスタイルと距離の置いた、陶芸のあり方が追求されていた。ダックワースは終生、土を素材にした彫刻を追求し、作品が小さくても、陶が彫刻的造形に向いているということを示した。イギリス時代にはNo.75 のような日用陶器も手がけ、渡米後は陶の彫刻家(ceramic sculptor)として活躍した。
大戦後、イギリスの美術学校では産業デザインではなく工芸(クラフト)として陶芸を教えることが盛んになり、多くのスタジオ・ポターが誕生した(註13)。また、リーチ工房のみならず、ダーティントン、ウェンフォードブリッジ、ウィンチコムなど地方窯から作家が育った。概してイギリスの現代陶芸は二分されていく。一つはリーチ派に代表される、東洋陶磁と英国古陶を背景に持ち、健康的な美しさと作陶における正しい姿勢を規範とする「倫理陶器(ethicalpots)」の系譜である。しかしその内実もまた一枚岩ではない。
リーチ工房は、経営を引き継いだデイヴィッド・リーチによる家庭用廉価版スタンダードウェア(定番商品)の通信販売や重油窯の導入、またジャネット・リーチが始めた研修生制度により、バーナード・リーチのデザインは維持しながらも時代の要請に応えていった。濱田篤哉、舩木研兒、市野茂良らによる国際的な交流は、今日のリーチ工房に通ずる特色となって続いていく。また彫刻の素養のあるジャネット以降、ジョン・ベディングやジェイソン・ウェイソンのように、日用陶器における表現的な造形性が、リーチ工房の芸術的な側面として脈々と流れていく。
バーナード・リーチの「正統」、その精神性は、むしろリーチ工房の外側に引き継がれているとも言える。ジョン・リーチや、重油窯で黙々と堅牢なうつわを作り続けるリチャード・バターハムには、工人としての姿勢が徹底的に貫かれている。
現代の視線から東洋陶磁に共感する作家として、フィル・ロジャースは濱田庄司への憧憬を抱き、作品と周辺の歴史の研究を作陶に反映させている。ロンドンを拠点とするリサ・ハモンドはいわゆるリーチ派ではないが、美濃のやきものを美意識の拠り所に、志野とソーダ釉による薪窯焼成を追求する。
カーデューに学び、精神性を受け継ぐ系譜の作家として、薪窯により質実剛健な陶器を作り続けてきたスヴェン・ベイヤー、伝統的な英国スリップウェアを復興し、濱田庄司の流描きのごとく独創性のあるスリップの技法を見せるクライヴ・ボウエンらがいる。
今世紀に入っても、イギリスの北部や南西部で、いわゆる日用陶器を制作する作家たちが少なからず存在する(No.96-104)。その作家たちは、自然豊かな環境を直接源泉としながら、自然への畏敬をモチーフとして表現する。釉薬の色彩を豊かに駆使し、具体的で絵画的な表現が顕著に見られるのは、ウィリアム・モリス以来の自然や装飾に対する英国特有の志向が脈々と続き、今なお生き続けているからとも言えるだろうか。大文字のスタジオ・ポタリーの歴史が土の抽象として展開してきたのに対し、その潮流だけでは汲み取ることができない、イギリス陶芸の裾野の広がりが見えてくる。
イギリス現代陶芸を語るうえで不可欠なもう一つの系譜が、リーやコパーらに美術学校で学んだモダニストたちの流れである。1970年代、80年代になるとニュー・セラミックスと呼ばれる世代が現れ、表現の多様化が進む。特に80年代は「うつわ」というテーマが造形的にも哲学的にも再解釈が行われた時代となった。ゴードン・ボルドウィンから、アリソン・ブリトンやキャロル・マックニコル、ケン・イーストマン、マグダレン・オダンドウまで、現在も活躍する実力作家の枚挙にいとまがない。本展で紹介しているエリザベス・フリッチは、うつわの形態の持つ視覚性や立体性のあり方に新たな見方を提示した。マーティン・スミスはうつわが規定する空間性の問題を提起する。ティナ・ヴラソプーロスはうつわの形態を通じて自身の五感で得た感覚を表現し続けている。フリッチらの系譜に位置し、21世紀においてなお静かに展開し続けているのがジェニファー・リーである。作家の記憶の深層、指先で接した森羅万象が、土の色層やうつわの姿となって表れている。
しかし、以上の二つの系譜がありながらも、英国スタジオ・ポタリーの現代の醍醐味は、日用陶器と鑑賞陶器、機能性と彫刻性、うつわとオブジェといった基軸が対立することなく共存しているところにある。つまり、どちらとも言えないような作風、あるいは両面性を持った作風を展開する作家が少なくない。これはイギリス陶芸のメインストリームにおいて、作品が概して巨大化したり、建築化したりしなかったこと、つまり、作品の細部に宿る工芸的な思考(素材や手法から出発する身体的思考や技術的な洗練)が作り手たちの間で尊重されてきたからだと筆者は考える。
ウォルター・キーラーやジャック・ドハティは、塩釉やソーダ釉による物理的効果を探究し、土の造形としての確かさを追求しながら、表現性の強いうつわを手がけている。うつわ上で抽象絵画のごとく素材が戯れ、その物質性が観る者に作用する。スリップウェアに現代的解釈を加えたディラン・ボウエンは、その作用を巧みに表現としてとりいれている。
1990年代以降、ロンドンでは異ジャンルの作家たちが仕事場をシェアする共同スタジオ(cooperative studio)が盛んである。南ロンドンのヴァンガード・コート・スタジオでかつて共に制作していたエドモンド・ドゥ・ヴァールとジュリアン・ステアは、ともに言語と制作の両面からうつわに哲学的考察を加え、英国スタジオ・ポタリーに新たなフェーズをもたらした。彼らは依然としてポットを作りながら、うつわをインスタレーション的にみせ(註14)、うつわがうつわであることの蓋然性や、陶芸に付随する身体性、やきものが喚起する集団的/個人的記憶のあり方を問う。ドゥ・ヴァールが自身の「日本での磁器との出合いの体験の象徴」と語る《things exactly as they are》(No.119)。ステアの《台座に置かれた5つのティーポットとキャディ》(No.120)は、日常のうつわの存在性や台座の問題を提起する。両作家は今では世界的なギャラリーで発表し、コンテンポラリーアートの文脈に位置づけられたと言える。しかし注目すべきは、彼らがコンセプトによって土という素材を選んでいるのではなく、陶やうつわからコンセプトを引き出していることである。したがって、コンセプトの源となる「もの」としての洗練、行き届いた工芸としての美しさが作品成立の大前提となっている。なぜなら、細部の洗練が、作品の核心の深化と直結してくるからである。ここに、そもそもスタジオ・ポタリーの出発点にあった美術と工芸の問題を超克する可能性がある。
彼らに師事した作家たちは、工芸的思考が生きたうつわを丹念に制作するスタジオ・ポターである。クリス・キーナンは天目釉と青磁釉に夜空と天空の色を見出し、うつわ同士を戯れさせた遊び心ある磁器を手がける。カリーナ・シスカートは母国ブラジルの建築群に触発され、ロクロで成形してパーツを組み合わせるという手法により構築物として器形を立ち上げる。サン・キムは、土の性質をいかして清潔感と造形の程よい緊張感を豊かにみせる。
以上、英国スタジオ・ポタリーの流れを概観したが、この展覧会は濱田庄司とリーチに始まる英国と益子の個人陶芸を並行して見つめることに主眼を置いており、イギリス陶芸史を網羅することは意図していない。ここでは、本展の出品作品のいくつかを手がかりに「うつわ」の表現の変遷を見つめることに焦点を絞った。古今東西、うつわは日常陶器から表現的なものまで「陶芸の歴史やさまざまな文化と関連した陶芸のシンボル」(註15)であった。作り手がうつわをどのように捉えてきたのかを見つめることは、その陶芸の核心に触れることに通ずる(註16)。
英国スタジオ・ポタリーにおけるうつわの表現の変遷を見つめると、作家意識の表れ方、東洋と西洋、釉薬の表現性、うつわの造形性、自然観などをめぐる価値観の問題が浮上する。これらは、英国スタジオ・ポタリーの特色であるばかりでなく、近現代陶芸全体に通ずるトピックとしても捉えることができるだろう。益子陶芸美術館は、25年間(特にここ10年間)の活動を通じて、益子のローカルな陶芸史とも絡める形で英国スタジオ・ポタリーを少しずつ扱ってきた。本展で紹介しているのはその蒐集の成果である。益子の陶芸の歴史は、ローカルなやきもの史であると同時に、近代日本の陶芸史にも関わり、かつ海外の陶芸の動向と軌を一にしている。益子は極めて独自な仕方で世界に開かれているのである。一個人や一地域の出来事が、いかに世界の歴史の成り立ちに関わっているのか、本展によってあらためて考える機会となれば幸いである。
(益子陶芸美術館学芸員)
| 註1 | 「東と西の結婚」のヴィジョンは、古今東西のやきものの「参照」、「解釈」、「統合(=結婚)」という三段階を経て、制作プロセスに反映される。鈴木禎宏『バーナード・リーチの生涯と芸術』213-243頁、ミネルヴァ書房、2006年。 |
| 註2 | Edmund de Waal, Bernard Leach, pp.13-15, Tate Gallery Publishing, 1998. |
| 註3 | 模様(pattern)とは本来的には「独創的なモチーフ」を意味し、「繰り返し(repetition)や模倣(copy)ではない」とリーチは述べている。Bernard Leach, A Potter's Book, p.101, Faber & Faber, 2011. 石川欣一訳『陶工の本』177頁、河出書房新社、2020年。 |
| 註4 | 後述のマーティン兄弟以外には、ウィリアム・ド・モーガン、クリストファー・ドレッサー、ロジャー・フライが主宰したオメガ工房などが挙げられる。 |
| 註5 | Malcom Haslam, The Pursuit of Imperfection: The appreciation of Japanese tea-ceremony ceramics and the beginning of the Studio-Pottery movement in Britain, The Journal of the Decorative Arts Society 1850 – the Present, No.28, ARTS & CRAFTS ISSUE, pp.148-171, 2004. |
| 註6 | エマニュエル・クーパー著、西マーヤ訳『バーナード・リーチ 生涯と作品』159頁、ヒュース・テン、2011年。 |
| 註7 | Sarah Riddick, Pioneer Studio Pottery The Milner-White Collection, p.118, Lund Humphries, London, 1990. |
| 註8 | 前﨑信也「バーナード・リーチの窯を建てた男―松林靏之助の英国留学―(1)」、『民藝』717号、日本民藝協会、2012年。 |
| 註9 | Julian Stair, The Spark that ignited the flame- Hamada Shoji, Paterson's Gallery, and the birth of English studio pottery, Ceramics, Art, and Cultural Production in Modern Japan, Sainsbury Institute, 2020. |
| 註10 | Bernard Leach, Ibid., p.24. |
| 註11 | カーデューの追悼特集に陶芸家ヴィクトル・マーグリー(Victor Margrie)は以下の言葉を寄せている。"Was he an emissary of the glories of English slipware now past and forgotten, or was he the true guardian of an English pottery tradition which was to be preserved and extended into the present?" "Michael Cardew – Pioneer Potter", Ceramic Review, No.81, p.12, May-June 1983. |
| 註12 | 金子賢治「ルーシー・リー作品の源泉」、『Lucie Rie Vol.2』、水戸忠交易、2007年。 |
| 註13 | 以下、戦後の英国スタジオ・ポタリーについては、Oliver Watson, Studio Pottery, Phaidon Press, 1994. |
| 註14 | うつわのインスタレーション化の先例としては、本展では触れられなかったが、グイン・ハンセン・ピゴットがいる。ピゴットは、ジョルジョ・モランディの静物画に触発されて器物を画面のごとく並べた。 |
| 註15 | 三浦弘子「魅せる"うつわ" というシンボル」、『うつわドラマチック展』181-184頁、滋賀県立陶芸の森、2017年。 |
| 註16 | 近年、英国スタジオ・ポタリーの展開を「器種」という観点でみせた展観としては、Things of Beauty Growing: British Studio Pottery, Yale University Press, 2017. |
※文中の「No.」は、本展図録の作品番号
※本研究の一部は、公益財団法人 美術工芸振興佐藤基金(「イギリスのスリップウェア研究-マイケル・カーデューを中心に-」)の助成を受けたものです。
| 日時: | 2020年10月11日(日) ※終了いたしました 1回目 13:00開演(12:30開場 終了予定時刻14:00 途中休憩有) 2回目 16:00開演(15:30会場 終了予定時刻17:00 途中休憩有) |
| 演奏者: | 奥村 琳(ヴァイオリン)、小林 清美(ピアノ) |
| 内容: | 濱田庄司やバーナード・リーチと同時代を生きた作曲家による、クラシック音楽の佳曲をお届けします。 |
| 曲目: | フランク ヴァイオリン・ソナタFWV 8 M 8 イ長調より第一楽章、第四楽章ほか |
| 入場料: | 無料 |
| 会場: | 益子陶芸美術館/陶芸メッセ・益子内 益子国際工芸交流館アトリエ |
| 席数: | 各20席(計40席) ※満席となりました。キャンセル待ちを受け付けております。 |
| ご予約方法: | 電話(0285-72-7555)先着順。 受付時間 開館日9:30~17:00 |


ご来館の際は感染症対策へのご協力をお願い申し上げます。
日時:8月1日(土)14:00~ ※終了いたしました
場所:益子陶芸美術館展示室内
講師:横堀聡、松﨑裕子(当館学芸員)
本展覧会の内容について、当館学芸員の2人が作品を前にわかりやすく解説します。
※予約不要・要観覧券
なお、ご来館の際はマスクの着用および手指の消毒等、感染症対策へのご協力をお願いいたします。入館者が多数となった場合には、入場制限をさせていただく場合もございます。
また、今後の状況により予告なくイベント等を延期・中止する場合がございます。その際は当館HPおよびSNSにてお知らせしますのでご確認ください。
※今後の状況により、展覧会予定に変更が生じる場合がございます。最新情報は、当館ホームページ・Facebook・Twitter 等でご確認ください。